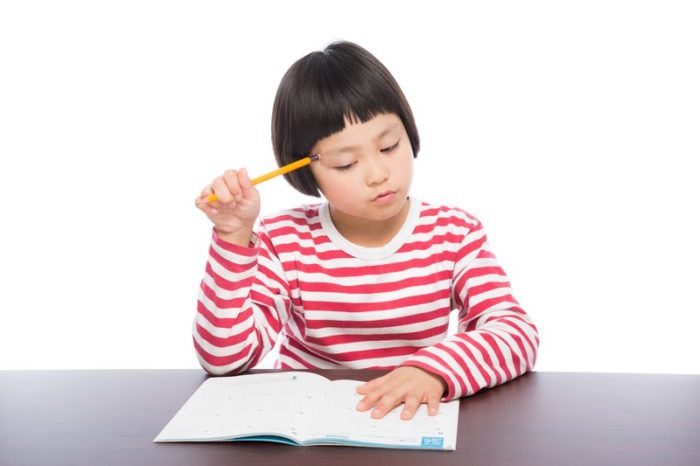2019年4月30日に現在の天皇陛下が退位され、5月1日に現在の皇太子殿下が新天皇として即位されます。
それによって平成の時代が終わり新しい元号の時代が始まりますが、2019年といえば平成31年ですよね。昭和が64年まであることを考えたら少し短いような。というより昭和が長い?
「天皇が替わると元号が替わるということはなんとなく知っているけど、それ以外のことはあまりわかってない・・・。」
そういった方も多いのではないでしょうか?私もギリギリ平成生まれなこともあり、正直知らない部分も多いです。
そこで今回は、なぜ昭和が長いのか、皇位継承と改元の歴史や仕組みについて調べてみました。
2019年4月1日11時40頃、新元号は令和(れいわ)と発表されましたね!
令和という言葉は万葉集、梅花の歌の序文からとられたもので
「厳しい寒さの後に見事に咲き誇る梅の花のように、1人1人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる日本でありたい」
との願いが込められているそうです。
スポンサーリンク
目次
昭和天皇が即位したのはなんと25歳のとき!
昭和天皇は1901年(明治34年)生まれなのですが、なんと天皇に即位されたのは1926年。つまり25歳の時に第124代天皇となり昭和がスタートしたのです。すごい若さですね!
それから1989年に御年87歳で崩御されるまでの約64年間が昭和の時代となりますので、昭和が他の時代と比べて長い理由は、即位された年齢が若く、長生きされたため在位期間が長かったからということになりますね。
《昭和天皇の略歴》
1901年(明治34年)4月29日ご誕生
1912年(明治45年(大正元年))7月30日11歳で皇太子となる
1926年(大正15年(昭和元年))12月25日践祚
1989年(昭和64年(平成元年))1月7日崩御
践祚(せんそ)・・・天皇の位につくこと
崩御(ほうぎょ)・・・天皇・皇后・皇太后・太皇太后が死ぬことの尊敬語
参考:宮内庁HP
大正や明治は?
昭和天皇の即位が若干25歳で行われた理由として、お父様である大正天皇が若くして崩御されたことが挙げられます。
大正天皇が即位されたのは1912年33歳の年ですが、崩御されたのは1926年47歳の年です。大正天皇は幼少期から健康状態が良いとは言えず、そのため大正時代は15年までと短くなりました。
ちなみに明治は45年と長いですが、明治天皇が即位されたのは満14歳のときでした。今なら考えられないですね!
ちなみに天皇が替わると気になるのが、祝日である天皇誕生日。
現在の天皇陛下のお誕生日である12月23日が今後祝日として存続するのかはコチラ↓の記事で紹介しています。
⇒元号変更で現在の天皇誕生日は祝日じゃなくなる?過去の経緯から考えてみた
スポンサーリンク
皇位継承と改元
元号法(1979年(昭和54年)制定された元号に関する法律)により、皇位の継承があった場合に限り元号を改めるとされていますので、現在の法律ではそれ以外の理由で元号を変更、または皇位の継承があったのにもかかわらず元号を存続させることは認められていません。
元来、元号は天皇が定めるもので、初めは同一の天皇の下で何度も元号を変えることがありましたが、1868年(明治1年)に同一の天皇の一代は同じ元号とする、いわゆる一世一元制が定められました。
ですが規定が置かれている旧皇室典範がのちに廃止されたあと、かわって制定された現在の皇室典範(昭和22年法律3号)は元号について言及していないので、戦後長い間元号は法的根拠をもたない慣習上のものにすぎませんでした。
しかし、日本に伝統的に用いられてきた元号を法律上認知し、それに正式の位置づけを与えよとの声が高まり、1979年に元号法(昭和54年法律43号)が制定されました。
参考:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
生前退位
皇位というのは本来終身制のものであるため、皇室についての基本法典である皇室典範では、現状、皇位の継承は天皇の崩御に限られていました。
ですが現在の天皇陛下(今上天皇)が健康上等の理由から退位のお気持ちを話されたことにより、天皇陛下の退位を一代限りで認める特例法が参院本会議で可決され、成立しました。
ポイント
ポイントとしては皇室についての基本法典である皇室典範の規定を変更したものではなく、今回に限り特別に生前退位を認めたというところです。
よって今後も同様に生前退位が認められるかはまだわかりません。
ですが天皇陛下のお体へのご負担や社会システムなどを考えると、今回のようにご存命のうちに皇位を継承された方が理にかなっているのではと思います。
元号はなくなる?
現在の法律上、皇位の継承があれば元号は替わることがわかりました。人間の生死にかかわってくる問題なので一概には言えませんが、現代の社会情勢から考えると昭和のように半世紀以上同じ元号が続くことは稀であり、今後も30年前後で元号の変更があると考えられます。
そうなると問題になってくるのが契約書や身分証明書(運転免許証等)、システム上の変更手続きです。
人生80年としても2回は改元を経験するペースになりますし、いつ変更になるかはわからないため、改元のたびにシステムを組みなおしたり、書類の変更手続きが必要になったりする可能性があります。
それって正直ちょっと大変じゃないですか?
私は現在会社の総務で働いていますが、基本的に契約書や申込書などの記入欄は和暦表示が多いですし、それを一つ一つ変更するのはちょっと・・・と考えてしまいます。
それが100年に一度とかであればいいかもしれませんが、何十年かの間に何度も起こりうると考えると現代に即していないのではと思います。
日本の伝統として元号は残すべきとしても、基本的な書類やシステムは全て西暦表示で記載するなど、時代にあった仕組みを考えるべきではないでしょうか?
まとめ
昭和が他の時代に比べて長い理由は、即位した年齢が若かったからということがわかりました。
先のことはどうなるかわかりませんが、昭和より長い元号はこれからも出てこなさそうですね。
私も改元は初めての経験となりますが、一つの時代が終わると考えると少し寂しい気持ちもあります。
なんにせよ、改元は私たちの生活にも直接かかわってくる問題ですので、これを機に少し自分でも考えてみるのもよいかもしれません。
スポンサーリンク